はじめに
こんにちはChaiです。今日は普段の生活の中で、仮説→検証のサイクルを素早く回すことの優位性とそのためにできる工夫について話をしたいと思います。
まずはじめになぜこのサイクルを素早く回すことが大切かということについて簡単に述べた後、日常生活でどのような工夫をすればこのサイクルを素早く回せるかについて考えたいと思います。
仮説→検証のサイクルを素早く回すことの優位性
日々、新しい価値が生まれています。今まで大勢の人々が思いもよらなかったアイディアを形にしてバズる人がたくさん出てきています。彼らのようになるためにはどのような思考や行動指針が必要なのでしょうか。
答えは仮説→検証のサイクルを素早く回すことです。
この「仮説→検証のサイクルを素早く回す」を続けることで大当たりは引けないまでも人生はかなり楽になると筆者は考えています。
まず出発点は仮説を持つことです。仮説の段階では突拍子もないように思えるものも排除せずにおくべきです。スティーブジョブズは以下のように言いました。
多くの場合、人は形にして見せて貰うまで自分は何が欲しいのかわからないものだ
この言葉は「普通に考えて人が欲しいと思っているものも正しいとは限らない、こちらから提示して初めて本当に人が欲しいものがわかる」ということだと思います。
Apple社はご存じの通り、iPhoneを世に送り出しましたが、これは当時の携帯電話市場を考えると物理的にボタンをなくすという突拍子もないアイディアだったと思います。しかしApple社はこの仮説が正しいかもしれないとしてiPhoneを発売しました。
このタイミングで「いや、こんなもの売れるわけない」とアイディアを排除してしまえばiPhoneは今も世の中にないはずです。
いま私たちの現代から過去を見てみると、このヒットは必然だったように感じますが、当時は売れるかどうか確信が持てない中での販売だったと思います。
しかし、製品が売れなかったとしてもまた新しい製品でチャレンジできるので特に問題はないと私なら考えます。(もちろん損失は痛いが)
iPhoneの例は極端ですが、現代をよく表していると筆者は考えています。つまり現代は
何が正解か(何がヒットするか)わからないし、成功率よりも一度の成功の影響があまりにも大きい
時代だと考えています。
このような時代においては、様々な仮説を検証してみること、小さな失敗を受け入れ大きな成功を目指すことが適切だと考えています。
そのためには先ほどから述べているように仮説→検証のサイクルを素早く回すことが大切だと考えています。理由は2点あります。
とにかく試行回数が大切なので素早いフィードバックが有効である
まず初めに、素早いフィードバックではすぐに結果が出るので次の打ち手を繰り出しやすいという点が挙げられます。何が正解かわからない世界において試行回数は正義です、この素早いフィードバックと次の打ち手のサイクルにより、多くの試行回数を稼ぐことができます。考えに考え抜いた1つの施策より数うちゃ当たるで1000回試行した人のほうが成功する時代です。
フィードバックにより仮説は進化する
2点目はフィードバックにより仮説が進化するという点です。フィードバックを受け取ると新しく考える変数が増えます。これにより前の仮説が新しいものへと進化するはずです、ここでは大胆な軌道修正が必要になることもあるかと思いますが、必要なステップとして取り組みましょう。
以上2点より、素早い仮説→検証のフィードバックは何が正解かわからない世の中において、大きな影響を持つビッグヒットを生み出す唯一の方法だと考えられます。
これは企業に限定されることではなく、個人の人生にも応用できるものであると筆者は考えています。いや、むしろ個人のほうがより、素早い仮説→検証サイクルを回すことが可能であるはずです。企業では仮説を立ててから検証するまでにどれだけ早くても1年単位の時間とものすごいお金が必要になるはずです。しかし個人レベルであれば、日々の生活から仕事までよりミニマムなサイクルを回すことが可能であり、これこそ個人の優位性であると考えます。
じゃあ、なにをすべきなの
では仮説→検証のサイクルを素早く回すためにするべきことは何でしょうか?
筆者は3点あると考えています。
身軽でいること
まず1点目は身軽でいることです、これがなぜ必要かというとサイクルを回すための腰を軽くするためです。この身軽でいることというのは物理的に身軽でいること(ミニマリスト的に生きること)と精神的に身軽でいることの両方を含みます。
例えばなにか新しく始めるときに、いまあるものが多すぎて腰が重いというのはそれだけでサイクルの遅れを招きます。この身軽さという概念は打席に立つことの最大化と直結しているかつ、フィードバックに対する柔軟な姿勢、自分の意見をいとも簡単にひっくり返す性質と直結しているのでぜひとも身に着けたいものです。お金をかけて時間を作ることも大切だと考えます。参考記事
インプットを常に最大化すること
次にインプットを最大化するということです、仮説→検証から得られるフィードバックからのインプットはもちろんのことですが、それ以外の場所からも様々なインプットを取り入れたいところです。結局優れたアイディアというのは既存のアイディアの組み合わせでしかない、というのは有名な話ですがそもそも既存のアイディアを知らないと組み合わせは不可能なので、様々な種類のインプットをしたいところです。
ここでのインプットというのは意識的と無意識的なインプットの両方があります。
意識的なインプットというのは自ら本やインターネットから探してくるものになります、仮説の磨きこみに対しては効果的ですが意外なアイディアは生まれにくいという側面があります。
無意識的なインプットは意識的なインプットの反対です。ここで無意識的なインプットとは何気なく参加した飲み会で聞いた話などがあります。これらはほとんどが仮説と関係のないものですが、自分の中で引っかかった概念が意外な組み合わせとして表出することがあります。
プロセスそのものを楽しむこと
最後はプロセスそのものを楽しむということです。
これは精神論的な話になりますが、正直この仮説→検証のサイクルでは上手くいかないこと、失敗だとわかることが大多数を占めることになるかと思います。それでも大切なのはサイクルを回し続けること、打席に立ち続けること、ガチャを回し続けることです。
この継続のためにはプロセスそのものを楽しむ必要があると筆者は考えています。例えば、SNSで投稿を伸ばしたいとして、仮説としてトレンドワードに関連した投稿をするというものがあったとします。この仮説ではあまり投稿が伸びなかったとしても、前回の投稿より良くなった部分や、その投稿をするにあたって色々調べたことで自分の知識欲が満たされたことなどにも目を向けたいです。
終わりに
仮説→検証のサイクルを素早く回すことの優位性と、方法についていくつか書いてみました。
筆者自身まだまだこのサイクルを試行錯誤しながら改善している段階ではありますが、皆さんの役に立てればうれしいです。
| 仮説思考 BCG流問題発見・解決の発想法 [ 内田和成 ]価格:1760円 (2025/1/10 11:16時点) 感想(35件) |
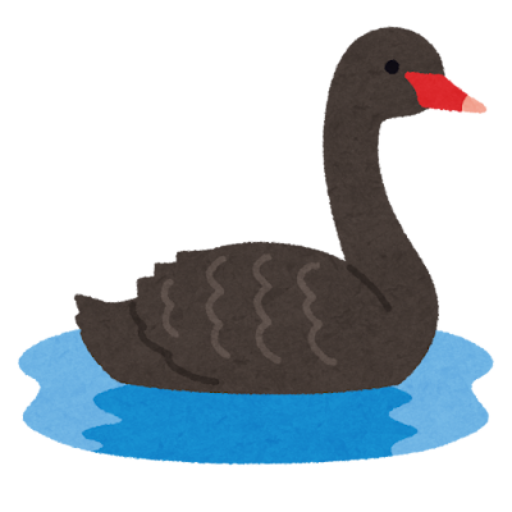
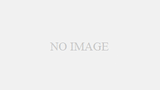
コメント